校長先生のイメージと実際の役割・仕事
このブログをお読みの皆さんは校長先生ってどんなイメージがあるでしょうか?
毎週月曜日の授業開始前に全校生徒を集めて高いところから訓話をしている年配の先生というのが最大公約数のイメージだと思います。
多分当たらずとも遠からずでしょう。ただし、校長室に詰めていることが多いのでなかなかその実態は分からないと思います。
勿論、朝礼で話をするだけではないのは当たり前です。他にどんな仕事をしているのかと調べてみると、これだけの職務があります。まぁ忙しい身分ですが、要するに学校運営の最高責任者です。だから要所要所で学校全体の方向性を決定しなければなりません。その決定が的外れであれば責任を取らなければならない、だから他の先生より地位も高ければ給与も高いのです。
けれども、少し立ち止まってよく考えて下さい。与えられた権限に基づき指揮命令したとしても教職員の各先生が従わなければ何も出来ないのも校長先生です。
そこで、ではどうすれば教職員の各先生に言うことを聞いてもらえるのか、それにより円滑な学校運営が出来るのかということが問題になると思います。
一番大事な校長先生のお仕事
それはつまり、校長先生の仕事の中で何が一番大切かということになります。会社であれ学校であれ組織というのはそれぞれの構成員が与えられた役割を果たしてはじめて機能します。
校長先生の仕事は学校全体の方向性を決めて指示すること。
ということは、校長先生の仕事で一番大切なのは教職員など各構成員に日常的に全体の方針を理解させることです。教職員などに全体の方針とそれぞれの役割を理解させることで彼等が日常的に自分のすべきことを理解し行動しやすくするのです。
勿論、綺麗事だけではありません。中には反発したり、サボったりする人もいるかもしれません。そのためににらみを利かせる、監視するというのも必要でしょう。そのために人事制度があるのです。抜擢・降格、昇給・減給・・・、信賞必罰を徹底している組織ほど、成員のモラルは高いところで維持され、そこから生まれる財やサービスのクオリティが高いのは言うまでもありません。ただし、人事権を濫用すると人心が離れ、組織の士気が下がるので、その行使をする際には慎重に慎重を重ねて判断すべきなのは言うまでもありません。
そうすることで生徒やその保護者にも「この学校なら大丈夫」と安心を与えることが出来る筈です。
生徒に対してすべきことは?
学校、職員室という組織内部に関してはそれで良いとして、生徒に対してはどのように接すれば良いのでしょうか?
校長先生も一教師です。個別の生徒との接点はないかもしれませんが、生徒全体との接点はあってしかるべきです。その中で彼等とどのように接するべきか、考えない方が可笑しいというものでしょう。
それを考える前にまず学校における生徒の立ち位置を考えなければならないと思います。
少子化が深刻化する昨今において、子供の人権をより尊重すべきだという風潮があるように感じます。それはそれで結構なことだと思いますが、行き過ぎは考えものです。
具体的には生徒をお客様扱いして、注意すべき場面で注意しないという姿勢は改めるべきでしょう。
そりゃ確かに誰だって注意したりされたりというのは精神的負担が掛かります。注意する方は注意することで恨まれやしないかと思うでしょうし、注意された方はなぜ注意されたかを考えずに注意されたことだけを忘れないかもしれません。となると、何もしないのが一番ということになるでしょう。
けれども長期的に見てそれで良いのでしょうか?もしもそれで良いと言うのならば、教育あるいは教育機関というものは存在しなくても良いということになりそうです。
そう考えるならば、「生徒はお客様」という前提が間違っているのではないでしょうか?少なくとも学校にとって生徒は「ステイクホルダー(当事者)」あるいは「構成要素」の筈です。その学校が「良い学校」かどうかを左右する一要素と考えるべきでしょう(「良い学校」の基準はさておき)。
とするならば日常的に生徒に自分達がどのような立場にあるかを理解させることが必要な筈です。
それが朝礼です。
テーマを明確に、そのために必要なのは?
大半の生徒にとって大人の長話に付き合わされるなんて退屈この上ないことです。皆さんにも覚えがあると思います。通っていた中学なり高校の校長先生のする朝礼の訓話の内容を一つでも覚えている大人、どれだけいるでしょうか?
やっている校長先生の側も日常のルーティーンの一環としか考えていない人もいるかもしれません。それならやらない方がマシです。ただでさえ朝早くから出勤させられている他の先生方にとっても迷惑です。
折角大勢の前で話すのですから明確なテーマを持って話しましょう。テーマは何でも良い、と言いたいところですが自ずと決まることでしょう。
大体、どこの学校でも創立の精神なんて似たようなものです、中等教育機関に求められる教育と大学など高等教育機関に認められる「学問の自由」に本質的違いがあることを考えれば分かる筈です。
ある程度出来上がっている人間を相手にする大学と違って中学校・高等学校は人格的に未成熟な生徒を躾けることが社会的使命です。成熟した人格と発達段階の人格の大きな違いは責任を果たすことが出来るかどうか、あるいは責任という言葉の本質を明確に理解しているかです。
「自由」「自律」「自主」「平等」「博愛」「個性」・・・、大体どこの中学校・高等学校も創業者はそういうことを唱えて設立したと思います。それを校長先生が生徒にも分かるように、出来る限り具体的に-時にはちょっとしたウィットも備えて-話す、それが朝礼の本当の目的です。
そのためには創設者の掲げた理念に立ち返り・・・、と言いたいところですが、大昔の人間の考えがそのまま現代に通用するとも思えません。それを現代風にアレンジするのです。
例えば、「自由」とはどういう状態を言うのか、「自由」と「自律」の関係性とは何か、「個性」を「平等」に尊重するとはどういうことか・・・、以外と分かっているようで分かっていないことが多いと思います。どの程度具体的に話せるかという問題ですよね。
そのために必要なのは勿論本を読むこともそうですが、「一流」に日常的に接することです。「一流」というのは別に肩書きを指しているのではありません。医者であっても、弁護士であっても、大企業の重役であってもダメな人は五万といます。
「一流」というのは、肩書き云々ではなく自分の顔で仕事をしている人を言います。自分の責任で仕事をし、社会的信用を得ている人です。
そういう人と日常的に接していれば良いのです。何も改まって接すれば良いと言うことではありません。例えば、近所の繁盛するラーメン屋の大将の動きを何となく見ていても勉強になるでしょう。若い従業員をどうやって躾けているか、秘伝のスープを開発するまでにどんな苦労があったか、後片付けをどうやってこなしているか・・・、ひとつひとつの動きを見ていれば何となく見えてくるものがあります。それを先程言った普遍的な価値に当てはめて考える癖を付ければ良いのです。それが日常的に出来ていれば、朝礼で話す内容にも事欠かない筈です。
ただし、ここで一つ注意が必要です。くどくどしい長話をしないということです。逆効果です。話は明確かつ具体的に、そして端的にーそれがビジネスでも教育でもあるべき形です。
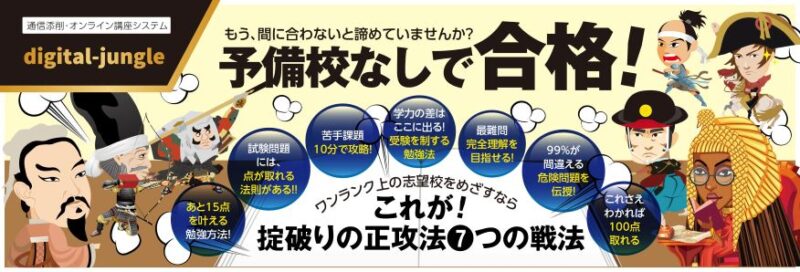
お申し込みは上記バナーをクリックしアップされるLPよりお願いします。
1 thought on “校長先生のお仕事~校長先生は何のために存在するのでしょうか?”