不感症?
今は色々変わってそれほどでもなくなりましたが、古典の教科書ガイドを紐解くとね、昔と変わらないなぁって思ったものです。昔と変わっていなくて懐かしいってのではなく、昔と変わってなくて全く進歩していないなという感想。
何十年も変わらず掲載されている『徒然草』とか『枕草子』の序文。恐らく指導者の中にはこれを暗誦しなさいと言う人もいると思いますが、これで良いのでしょうか?
個人的な経験で恐縮ですが、そういう高校教師に当たりましたが、ハッキリ言って面白いなんて全く思いませんでした。なんでこんな事をしなければならないのか、とさえ思いました。未だに思っています。ちゃんと説明してくれればあるいは納得したかもしれませんが、それもなかったのだから無理からぬ事だと思います。
記憶力は悪い方ではないと思うのですが、丸暗記というのは苦手で、「やれ」と一方的に命令されると拒否反応を示してしまうのは今も昔も同じ。自分と同じ人は多いのではないかと思います。
確かにそういうのが好きだとか、『徒然草』や『枕草子』の序文から無常観なりもののあはれを学ぶ事が出来るのだとか言う人もいるかもしれませんが、個人的には理解出来ません。大体、その程度の断片的な文章を一読した程度でそんなに深い理解に至れる訳がないでしょう。
有り体に言うと、これでは古典アレルギーを誘発するだけではないかとさえ思います。自分が不感症なのではなく、こういう指導しか出来ない人が生徒の感性に対して観察眼がないという意味で不感症なのではないかと思う次第です。
もっと楽に考えようよ
去年の大河ドラマと同時代のノンフィクション作品と言えば「大鏡」が定番です。実際『光る君へ』にも出て来た場面で、色んなところで取り上げられるシーンがあります。
若き日の藤原道長は兄・道隆の政権下で冷や飯ぐらいであった訳ですが、そんなある日、兄の屋敷で弓比べをする事になり、兄の息子でその後継者と目される伊周と対決することになりました。
「我が家から后が出るのならこの矢、当たれ!」「俺が摂関になるならこの矢、当たれ!」と叫びながら道長が矢を放ったらば的のど真ん中に当たった。これに圧倒された伊周の矢は的から大きく外れ、一連の流れを見ていた道隆はさも不快げに弓比べを中止させ、周りも興醒めになった…。
とまぁ、これだけの話ですが、大体の解釈はこのエピソードを持って、道長の剛胆さを称賛するものと解釈していますが、果たしてどうなのかなというのはあっても良いと思うのです、高校レベルの古典の話でも。
普通に考えてください、兄貴とは言え時の最高権力者の家に招かれて弓比べをさせられ、しかもその相手は兄貴の秘蔵っ子たるその息子なら、彼に花を持たせるはずです。それが叔父の甥へのノーマルな対応であり、大人のスマートな振る舞いというものです。
それが大人げなく甥を挑発するような振る舞いを取り、しかも勝負に圧勝するなんて大人げないにも程があります、そりゃ道隆も頭に来るのは当たり前だし、それを見ていた周りの人間も興が冷めない方が可笑しいでしょう。道長の剛胆ぶりを称賛するというより、道長の無神経さをなじる、それこそ今風に言うと「空気読めよ」と思って当たり前です。
ではなぜそういう記述がないかというと、その後道長が絶対的な最高権力者になったからです。だから「栴檀は双葉より芳し」となり、「剛胆ぶりに称賛」という風に(一種の)曲解がなされるわけです。
しかし、『大鏡』というと、道長の栄華を称賛と言うよりは批判的な歴史観を備えているという点で他の歴史書より優れているという評価が一般的であることを踏まえるならば、「空気読めよ」という解釈も一定の説得力があるはずだと思います。
ちょっとそういうの、勿体ないなと思うんです。
確かにこの小さなエピソードだけでそういう解釈に持ち込むのはやり過ぎだという批判もあると思いますが、ならば他の道長関連のエピソードをいくつか並べて彼の性格をプロファイリングするというやり方もあると思います。
これも立派な「探求」の一方向性ではないでしょうか。
もっと深く考えようよ
あるいは『方丈記』や『徒然草』なんかの中世初期・鎌倉時代の随筆なんて当時の仏教における支配的な思潮である無常観の影響をもろに受けていると言われますが、じゃあ「無常観」って何?って考えないと少し勿体ないなと思うんです。
辞書的な意味はここにあるとおりですが、だからって「人生ははかない、だからケセラセラ、なるようになるさ」とはなるとは限らないはずです。だったらあの時代、自殺者が一杯いるはずです(統計がないからどの程度か分かりませんが)。
そうじゃなくて「だからこそ今を一生懸命、大切に生きようよ」って発想もある筈なんです。仏教をちゃんと学んだことがないから確証を持って言えませんが、実際、鎌倉新仏教なんてそうじゃないですか。「現世利益」を肯定した親鸞とかもそうだし、日蓮に始まる法華宗みたいな祈りながら前に突き進むなんてノリの宗派だって上述した虚無感からは生まれにくいでしょう。鎌倉仏教が新興の武士階級や庶民に受け容れられたって事実もありますが、「無常観」が虚無的でありこれが支配的思潮であるとするなら、これをどう説明するのですか、と言うことになりますよね、論理的にも歴史的にも。
そういう事を踏まえてみると、無常観=ニヒリズムと記号的に結びつける事は出来ないわけです。
と、ここまで話を広げると、地歴公民でいう日本史とか倫理の話にも繋がりますよね。こういう授業をしてあげると、30人とか35人いてそりゃ全員という訳には行かないけれども、それなりの数の生徒は耳を傾けてくれる筈です。『大鏡』の場合なら、もっと俗っぽい話題ですから、それこそ大多数の生徒が面白がって話を聴くでしょうし、クリアな形で頭にも残る、そうなれば古典に関心を持つようになり、積極的に学習に取組み、得意科目になる可能性も高まる。あるいは他の科目との関連性も理解出来、他の科目の理解が深まることも期待できるはずです。
そして、これが「基本」を学ぶという事です。
「基本」とは、その分野で成果を出し続けるために不可欠な技能です。人間として多角的な視野を持ち、それぞれの関連性を理解した上で判断を下せるというのは生きていく上での「基本」です。最近喧しく言われている「情報リテラシー」にも通じる話ではないでしょうか?
私共、デジタル・ジャングルがやって来たことの一部、あるいは提唱する内容の一部ってのはこういう代物なのです。
無駄な努力は止めた方が良いですよ
6月頃にある学校の説明会に行きました。一日に7コマも8コマも授業をやっていて、如何にも「頑張ってますよ」感がにじみ出ている内容のお話しでした。
質疑応答の際に70年配くらいの学習塾関係者から「そんな旧来式の詰め込み教育で生徒の主体性は育まれるのですか?あるいはそれだけ授業を組んで、先生方はちゃんと授業の準備を出来るのですか?」という疑念・質問がありました。
学校側からは「授業の合間に教職員は教材研究などの準備をしているので大丈夫」「授業のコマ数も次第に減らす予定」という、それこそそれまでの説明になかったという意味で「取って付けた」ような返答がありましたが、個人的にはこの学習塾関係者の疑念は尤もだと思いました。生徒の自主性は言うまでもありませんし、そんな場当たり的なやり方で充分な授業の準備など出来ないと思うからです。それなりの学問的土壌とまとまった時間がないと良い授業のための準備は覚束ないと思わない方が可笑しいでしょう。無駄な努力は止めた方が良いと思います。
これらの課題を解決するために存在するのがデジタル・ジャングルであると改めて思い直した次第です。
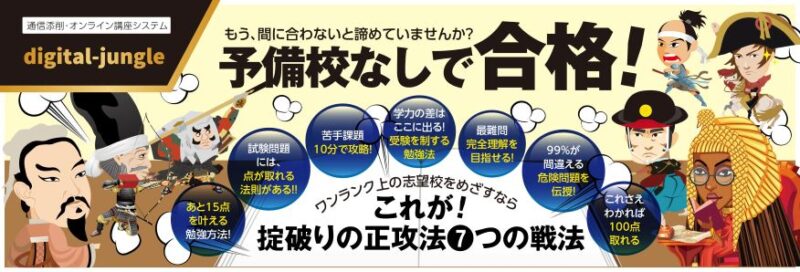
お申込は上記バナーをクリックしアップされるLPよりお願いします