案外分かっていない
商売柄今年も難関大学の入試問題に関して色々チェックをしているわけですが、同時に解答速報として出される予備校答案に関してもチェックしています。
流石に毎年というわけではないと思うのですが、「分かっていないなぁ」と思うことはある訳で、今年もちょっとそう思しき答案例を見付けました。
京都大学の文系国語の大問三、設問(一)です。詳細は各予備校が掲載している問題文か、これからリリースされる赤本ででもご確認下さい。
浅いんですよ~何を問われているかを考えよう
『とはずがたり』の一節が出典ですが、本文をざっと読んで浮かび上がるテーマって、「生への執着」とか「名誉欲」なんですね。
勅撰歌人を輩出する家に生まれた作者は様々な人生経験を積んでやがて出家の身となった、つまり世捨て人となった訳ですが、事ここに及んでつらつら我が身を省みて、勅撰和歌集に自作の和歌を選ばれる栄誉に浴したことがないことを嘆いている訳です。
出家=世を捨てた筈なのに、世俗の栄誉を渇望しているーそういうアンビバレントな精神状態がこの一節のテーマだと思われます。
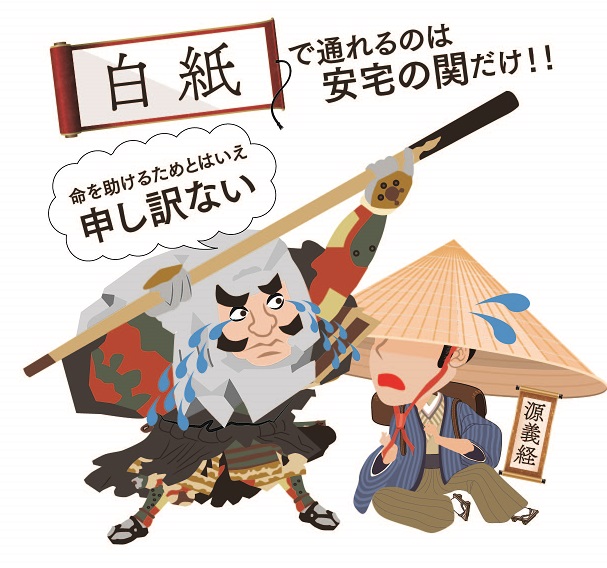 その上で傍線部(1)「つれなくぞめぐりあひめる」の意味を訊かれている訳です。
その上で傍線部(1)「つれなくぞめぐりあひめる」の意味を訊かれている訳です。
確かに「つれなし」という古語の意味は「通り一遍」というイメージから「冷淡だ」「よそよそしい」「さりげない」「何の変哲もない」というほどの意味になるでしょう。そして、それに基づいて書かれたのが各予備校の出した解答速報ですが、果たしてそれで良いのでしょうか?京大ともあろう者がその程度の出題をするでしょうか?
まぁ、出題者も少し不親切というか意地悪な出題をしたものだな、と思うのです。普通に考えれば「つれなくぞめぐりあひめる別れつつ」とした方がすっきりします、これでひとまとまりの意味内容ですから。
いずれにしても、この和歌全体を見ると「父大納言が亡くなってから三十三年にもなるけれども、色々な出会いと別れがあったようだ」というほどになる訳ですが、それが「つれなし」なんですよね。
出家したことも含めて色んな事があった割には勅撰歌人になるということもなければ、出家したのにまだ勅撰歌人になることに執着しているのですよ、この作者は。
それも含めて「つれなし」でないと、この後の話が続かない筈なんです。実際、話の流れが変わっていると言う事もなければ逆接の接続詞が出て来たって事もありませんから。
とするならば、この設問(一)は
「父の死後様々な出来事があったが、それを糧に勅撰歌人になる栄誉も得られず、出家したのに未だにその事に執着し、三十三回忌を迎えてしまったこと。」
というのが案外、出題者の求めているものではないかなと思うのです。
京大国語の解答欄のあり方に関しては、機会があればいずれ言及したいと思いますが、ここでは2行とされています。1行当り33~36字程度と考えると70字程度にまとめる能力が要求されます。ちなみにこの解答例は六十九文字です。
七十字というと、中途半端というか浅い理解しかしていないと多く感じる文字数、深読みして考える癖が付いていると少なく感じる文字数だと思います。大半の予備校答案を見ていて感じたのは前者でした。
浅い理解と深読み、どちらが良いかということもありますが、大学入試の制度趣旨が「大学という高等教育機関で学問研究に従事するに足る人材を選抜すること」である以上、多少深読みするくらいでも良いのではないかと思います。

1 thought on “京大入試古文(2024)設問(一)に関する考察~予備校答案の陥穽”